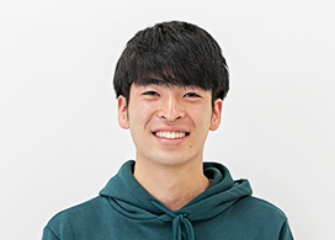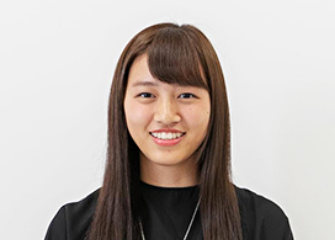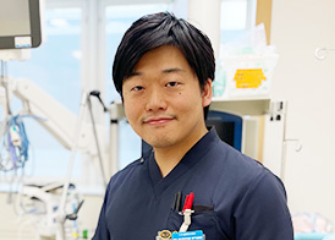学生や先輩に聞く
Voices

助けに手を差し伸べることのできる看護師になることを決意
看護師を目指した理由は?
決意したのは高校一年生の時です。
幼少期から看護師を目指していたのではっきりとしたきっかけは思い出せません。
しかし、決意したのは高校一年生の時です。
世界史の授業を通じて、助けを求めていても誰からも手を差し伸べてもらえない子供がいることに目を背けて生きていきたくないと感じました。そして「それならば、もともと目指している『看護』という面から助けよう」と決意しました。

慈恵のここが好き!

部活動が活発なことです。
慈恵は非常に部活動が活発でほとんどの学生が何かしらの部活動に所属しています。大学のルールで「最高でも週三まで」というルールがあるので、学業もバイトも友人との遊びも全てを両立しながら部活動を楽しめています。医学科の学生や、先輩、他大の医療系の学生など様々な人と関わることができます。私は弓道部に所属していて、昨年は仙台遠征など、たくさんの思い出ができました!
印象に残った講義を教えて!
一年時に通年で行われる、医療総論演習です。
この科目は医学科と合同で行います。一見、医療とは関係のないような議題について、医看合同で意見を出し合って議論したり、OBの方のお話を聞いたりして様々な形の「医療」を学びます。
医学科との距離が近い医学部看護学科だからこそ体験できる貴重なもので、非常に刺激を受け「医療」の知見を広めることができました。


 学科長ご挨拶
学科長ご挨拶
 6つの魅力
6つの魅力
 看護学科のあゆみ
看護学科のあゆみ
 カリキュラム
カリキュラム
 キャリア支援
キャリア支援
 キャンパス紹介
キャンパス紹介
 イベント・スケジュール
イベント・スケジュール
 部活・サークル活動
部活・サークル活動
 国際交流プログラム
国際交流プログラム
 データでみる Jikei’s Life
データでみる Jikei’s Life
 気になる!お金のこと
気になる!お金のこと
 1年生
1年生
 2年生
2年生
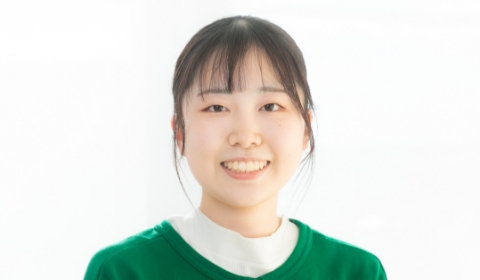 3年生
3年生
 4年生
4年生